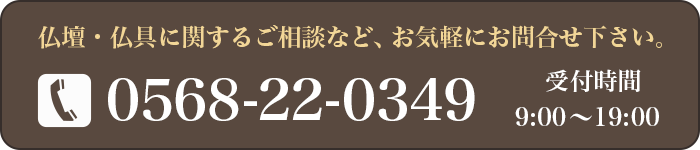- お盆
お盆と盆踊り
昨日は知人の方にお誘い頂き、名古屋市の中川区で
行われた金魚まつりに家族で行ってきました。
この時期は各地でお祭が行われ、気持ちが高揚しますね。
北名古屋市でも8月の3・4日と平和夏まつりが行われます。
お祭といえば、櫓(やぐら)を組んで盆踊りですね。
盆踊りはもともと、お盆に行われ精霊供養であったり
神様を祀るものであったり、お盆に帰ってくる
ご先祖様の御霊(みたま)を慰めたりなどの
仏教行事の意味合いがあります。
お盆の由来~1~で書かせて頂いた餓鬼道にいる
お母さんを救った目連さんの踊りなどが盆踊りのルーツです。
日本では、この目連さんの話から
平安時代に空也上人の念仏踊りによって始められました。
鎌倉時代になりますと、一遍上人により庶民を巻き込み
服がはだける程、踊り狂いました。
これは、念仏で救われる喜びを体現したものです。
この時代以降になってくると権力や財力を持った町民が様々な趣向を凝らしていきます。
また仏教行事よりも演芸に傾いていきます。
太鼓などの道具を使い、華やかな衣服になり、
音楽に合わせて踊るようになりました。
集落ごとに競い合うようにもなりました。
昔は当然、旧暦のお盆である7月15日か16日で行われていました。
十五夜と十六夜(いざよい)でどちらかの日には満月になりますので
月明かりで夜通し踊っていたみたいです。
今では、昔ながらの音楽だけではなく
アニメの曲やヒット曲で踊るのも多いですね。
時代と共に盆踊りも変わっていくのですね。