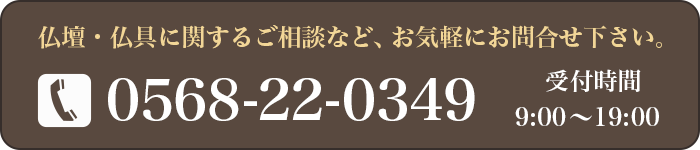- その他
お賽銭の意味
先日は稲沢市の国府宮神社にてはだか祭がありましたね。
正式な名称は儺追神事(なおいしんじ)です。
詳細は国府宮神社のホームページを見て頂ければ歴史等が分かります。
今回はお賽銭について書こうと思います。
皆さん、お寺や神社にお参りをするときにお賽銭をあげますが
お賽銭箱に「喜捨」や「浄財」と書いてあるのを見たことがありますか?
「喜捨」とは読んで字の如く、喜んで捨てるという意味です。
「捨」という字を見ると変な感じがしますが
仏教では「捨」という漢字は執着しないということです。
また、お布施のことなのです。
お布施というと、「あげること」と勘違いしがちですが
本来は「~させていただく」という感謝の気持ちが「施」です。
「施」は「欲しがらないこと」、「こだわらないこと」という意味もあります。
皆さんが物を捨てるときに、いらなくなったから捨てるのであり
その物に執着する心がないから捨てるのではないでしょうか。
喜んで供えさせて頂くということで「喜捨」と書きます。
「浄財」は寺社に寄付するという意味で
浄とは皆さんの綺麗で純粋な気持ちという意味ではないでしょうか。
前後しますが、お賽銭は祈願への対価ではなく、
仏さまや神さまに感謝の気持ちを伝えるお供え物の意味と
寺社の修繕等の費用に少しですがお役に立ててくださいという意味があります。
昔から、神道では散米(お米をまく)をして神さまにお祈りをします。
これは、神さまにお米を供えるという意味と
自分のけがれを払うお祓いの意味があります。
この慣習がお銭(おかね)をまく、
散銭になりお賽銭をあげて拝むことになりました。