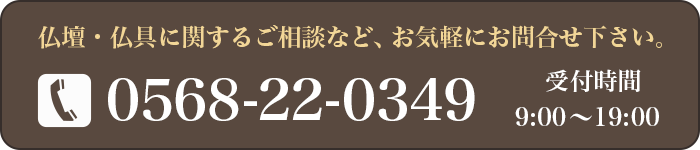- 仏具
打敷について
今日は打敷(うちしき)について書こうと思います。
打敷とは、お寺や仏壇の中に置かれている、卓(机みたいな形状)に飾る敷物です。
なかなか、言葉ではイメージできないと思われますが
蝋燭立て・花瓶・香炉が乗っている所の下に敷くものです。
打敷の起源としましては、お釈迦様が木陰や道端などで
座って説法をされる時にお弟子さんが
綺麗な布を敷いたことが所以といわれています。
日常は使うことはなく、
法事・彼岸・お盆などの仏事やお正月などに使います。
また、葬儀から四十九日までの間は、白い打敷を使います。
普段使われている打敷を裏返すと白い打敷になります。
一般のご家庭では、これを代わりに使うことが多いです。
季節によって夏用・冬用があります。
だいたい時期としては6月~9月ぐらいまでが夏用で
9月~5月ぐらいまでが冬用です。
ちょうど、今の時期から夏用に変えるといいですね。
物としては、人絹やミシンで刺繍されたお財布に優しいものから
正絹や手縫いで刺繍された高価なものがあります。
西陣織や伝統工芸品になると、とても高価になります。
基本的に洗うことができませんので、花瓶の水などにお気を付け下さい。
形状としては浄土真宗で使うのが三角で浄土真宗以外の宗派では四角です。
大きさは仏壇の大きさと比例しますので、
仏壇の大きさを言って頂ければご用意できます。
買い換える場合は、現在使われているものを
お持ち頂けるとサイズの間違いがないです。
柄も様々なものがありますので皆さんのお好みの柄をお選びください。
人の服と同じように打敷も季節によって変えると仏壇のイメージが違って見えますよ。